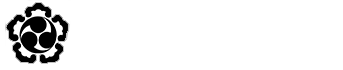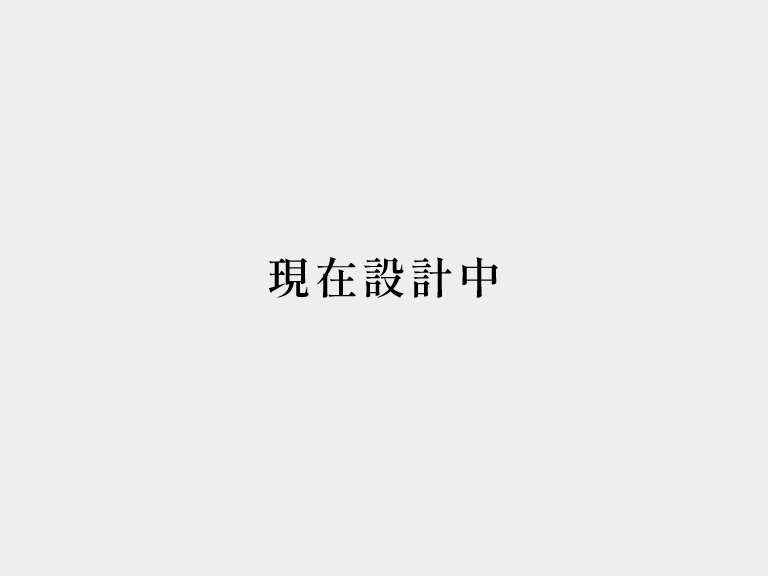雲心寺は遣迎山(けんこうざん)浄土院と号し浄土宗である。
この寺の前身は知多郡の清水村(現在の東海市荒尾町)にあった浄土宗・慈悲山普門寺であり清水村の丸根に通称一本松と呼ばれる地が普門寺の跡と伝えられている。この寺は熱田に移転後は観音堂のみが残り寺は村内に移り尼寺となった。今は知多新四国八十五番札所の清水時(せいすいじ)がそれである。
名古屋の伝馬町(現 中区錦一)の商人で萱津屋武兵衛こと近藤武兵衛という者がいた、彼は跡継ぎに先立たれ、身の不幸を嘆くあまり山伏に身をやつし、諸国行脚の旅に出た。
京都で法然院の万無和尚に出会い深く帰依することとなる。彼は元文四年(1735年)普門寺を川名村へ移し遣迎山称賛浄土院雲心寺と改め、更に翌年に現在地に移転したもので、
この地は志水甲斐守の下屋敷を買い求めたものである。
当時の本尊は一丈六尺の阿弥陀如来である、しかし実際には座像で高さ約2.4m位である。この本尊は興正寺の大日如来、栄国寺の阿弥陀如来と併せて名古屋三大仏と言われている。
建中寺の大基上人の発願で京都の仏師山本茂祐が製作し、文久三年(1863年)に完成した。
それまでの本尊は胎内仏として内に収められている。この仏像は同寺の本山、京都知恩院の阿弥陀堂本尊を模したものと言われ寄木造りの像に金箔をほどこした見事なものである。
文久4年に開眼供養がなされ常行念仏一千日の法要がなされた。
当時の金で300枚を要したと伝えられている。
この大仏は大変美しいということで昭和32年名古屋市文化財の指定を受けており、大仏が鎮座する本堂は明治19年に改築され京都の法然院を模したといわれる。
明治維新まで檀家はなく近藤家の縁続きで富豪の岡谷家・伊藤家(松坂屋)や佐々部家など、名古屋十人衆と言われた篤信家たちの寄進により守られてきた。